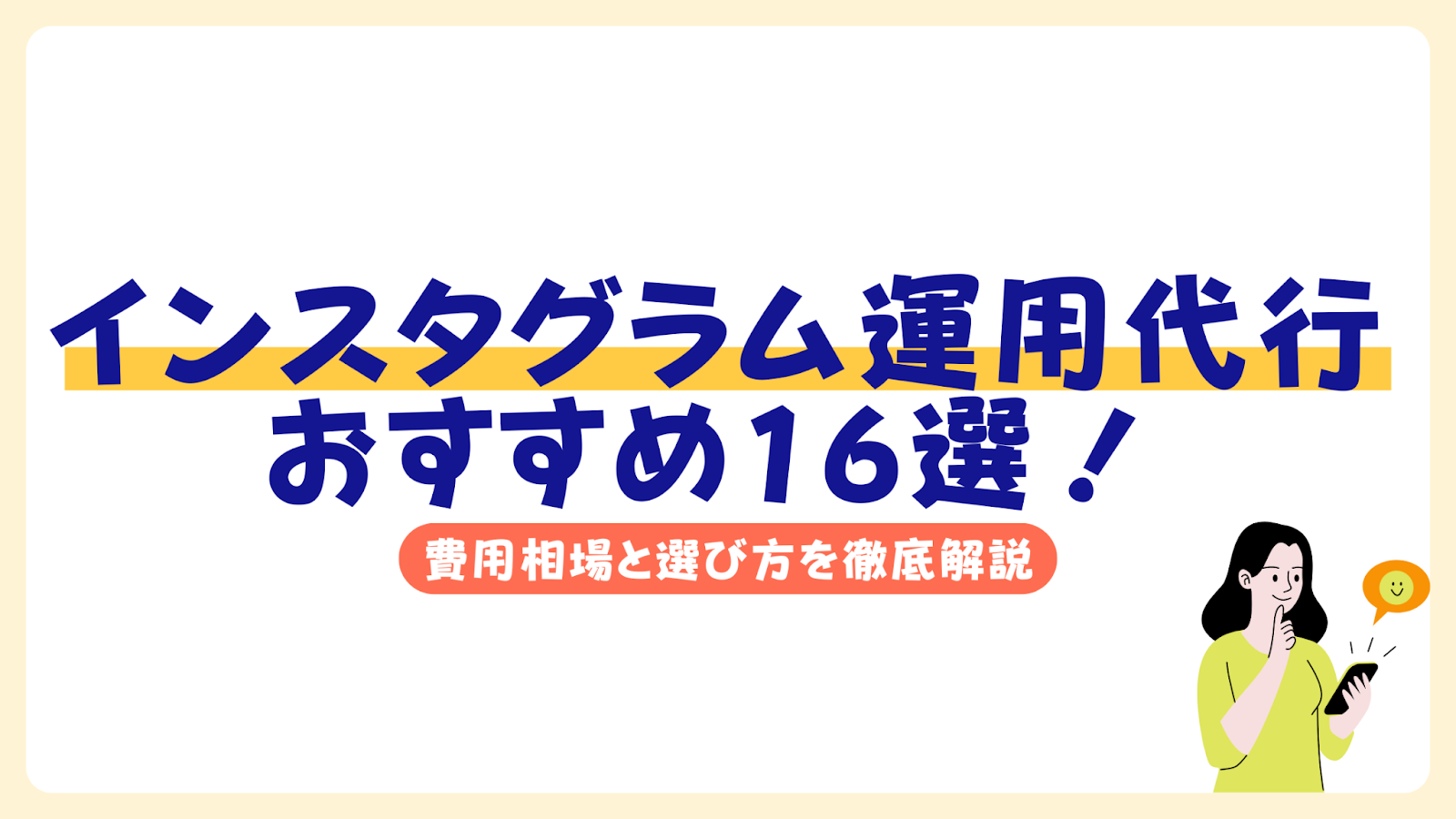【完全ガイド】企業のライブ配信活用|メリット・事例・導入ステップ・注意点まで

最近、企業がライブ配信を活用する場面を見かけることが多くなりました。セミナーや採用説明会、商品説明まで、さまざまな企業活動にライブ配信が取り入れられています。
でも実際のところ、「ライブ配信って本当に効果があるの?」「どんなメリットがあるの?」「導入するとしても、どこから手をつければいいの?」と疑問に思っている企業の方も多いのではないでしょうか。
実は、ライブ配信を上手く活用している企業は、従来の営業活動やマーケティングでは得られなかった大きな成果を上げています。コスト削減だけでなく、顧客との関係性強化や新しいビジネスチャンスの創出まで、その可能性は想像以上に広がっています。
今回は、企業がライブ配信を活用する具体的なメリットから実際の成功事例、導入時に失敗しないためのコツや注意点まで、実践的な内容を交えながら詳しくご紹介していきます。

東京大学卒業後、金融機関、スタートアップベンチャーを経て2016年にサイバーエージェントに入社してインターネット広告事業に従事した後、2020年7月に独立しました。
特に広告領域においてはプランニングから運用まで幅広く携わり、ナレッジは日本トップレベルだと自負しています。
◆ 経歴
2014:東京大学行動文化学科 卒業
2014:住友生命保険相互会社 入社
2015:株式会社RoseauPensant 入社
2016:株式会社サイバーエージェント 入社
2020:株式会社CYANd 創業/代表取締役就任
2022:株式会社Minato 入社/広告事業責任者就任
ライブ配信とは?企業活用が進む背景
まずは、ライブ配信の基本的な仕組みから、なぜ企業活用が進んでいるのかについて詳しく見ていきましょう。
ライブ配信の基本的な仕組み
ライブ配信とは、リアルタイムで映像や音声を配信し、視聴者と双方向のコミュニケーションを取ることができる配信手法です。従来のテレビ放送とは決定的に違い、コメント機能やチャット機能を使って、配信者と視聴者が直接やり取りできるのが大きな特徴になります。
この双方向性こそが、企業にとって非常に価値の高い特徴です。一方的な情報発信ではなく、リアルタイムで質問に答えたり、視聴者の反応を見ながら内容を調整したりできるため、従来の広告やプレゼンテーションよりもはるかに効果的なコミュニケーションが実現できます。
さらに、視聴者にとっても「参加している」という実感が得られるため、企業や商品への親近感や信頼感が大きく向上する傾向があります。
コロナ以降で定着した企業活用トレンド
2020年以降、新型コロナウイルスの影響でリモートワークが普及し、企業の会議やイベントもオンライン化が急速に進みました。その中で、単なるビデオ会議ツールではなく、より多くの参加者に情報を届けられるライブ配信が注目されるようになったんです。
特に、大規模なカンファレンスや全社会議、採用説明会など、従来は会場に集まって行っていたイベントをオンライン化する際に、ライブ配信の利便性が高く評価されました。参加者の制限がなく、全国各地から気軽に参加できることで、これまでリーチできなかった層にもアプローチできるようになった大きな変化となりました。
また、コロナ禍で外出自粛が続く中、企業と顧客をつなぐ重要なコミュニケーション手段としても活用されるようになり、今では業界を問わず多くの企業で導入が進んでいます。
なぜ今「ライブ配信マーケティング」が注目されるのか
スマートフォンの普及により、誰でも手軽にライブ配信を視聴できるようになりました。通勤時間や休憩時間、自宅でのリラックスタイムなど、さまざまなシーンで動画コンテンツを楽しむことが日常的になっています。
また、YouTubeやInstagram、TikTok、LinkedInなどの主要なプラットフォームでライブ配信機能が充実し、企業にとってもマーケティング手法の一つとして活用しやすい環境が整っています。
特に注目すべきは、ライブ配信の視聴者エンゲージメント率の高さです。通常の動画コンテンツと比較して、ライブ配信は視聴時間が長く、コメントやシェアなどのアクションを起こす確率も高いことが各種調査で明らかになっています。
さらに、Z世代や若年層の消費者にとって、ライブ配信は非常に親しみやすいコンテンツ形式です。彼らが購買決定を行う際の重要な情報源として活用されることも多く、企業にとっては新しい顧客層へのアプローチ手段としても期待されています。
企業がライブ配信を行うメリット
企業がライブ配信を導入することで、どのようなメリットが得られるのでしょうか。実際に導入した企業の声も交えながら、具体的に見ていきましょう
集客・認知拡大に効果的
ライブ配信は、従来の広告よりも親近感を感じやすく、企業や商品への関心を高めることができます。リアルタイムでの配信により、視聴者の注目度も高く、印象に残りやすいという特徴があります。
特に重要なのは、SNSでのシェア機能との相性の良さです。視聴者が「面白い」「為になる」と感じたライブ配信は、自然にSNSでシェアされやすく、それによってさらに多くの人に情報を届けることができます。このバイラル効果により、予想を上回る認知拡大を実現した企業も少なくありません。
また、ライブ配信は検索エンジンでの表示順位向上にも効果的です。GoogleやYouTubeなどの検索アルゴリズムでは、エンゲージメント率の高いコンテンツが上位表示されやすい仕組みになっており、ライブ配信はその条件を満たしやすいコンテンツ形式なのです。
顧客や求職者との双方向コミュニケーション
従来の一方的な情報発信と違い、ライブ配信では視聴者からの質問やコメントにリアルタイムで答えることができます。これにより、顧客との信頼関係を築きやすく、求職者に対しても企業の魅力をより深く、そして具体的に伝えることができます。
この双方向性は、特にBtoB企業にとって大きな価値があります。複雑な商品やサービスの説明を行う際、リアルタイムで質疑応答ができることで、従来のプレゼンテーションでは解決できなかった顧客の疑問や不安を、その場で解消することができます。
また、視聴者の反応をリアルタイムで確認できるため、説明が分かりにくい部分があれば即座に補足したり、関心の高い部分により時間をかけて説明したりと、柔軟な対応が可能になります。これは録画された動画コンテンツでは実現できない、ライブ配信ならではの大きなメリットです。
コスト削減と効率化(会場・交通費不要)
会場を借りる必要がなく、参加者の交通費もかからないため、大幅なコスト削減が可能です。
特に全国各地に拠点がある企業や、遠方からの参加者が多いイベントでは、その効果は絶大です。
実際に、ある製造業の企業では、年4回開催していた全国代理店会議をライブ配信に切り替えることで、年間約800万円のコスト削減を実現しました。会場費、講師の交通費、参加者の宿泊費などを合計すると、1回あたり200万円程度かかっていた費用が、ライブ配信では機材費と通信費だけで済むようになったのです。
さらに、準備にかかる時間も大幅に短縮できます。会場の手配、資料の印刷・配布、当日の運営スタッフの手配など、リアルイベントで必要だった多くの作業が不要になるため、企画から実施までの期間を短縮できるのも大きなメリットです。
時間や場所を問わず参加可能
参加者は自宅やオフィス、移動中など、どこからでも気軽に視聴できるため、これまで参加できなかった人たちにもリーチすることができます。育児や介護で外出が難しい方、遠方にお住まいの方、身体的な制約がある方にも情報を届けられるのは大きなメリットです。
この「参加のしやすさ」は、参加者数の大幅な増加につながることが多いです。ある企業では、従来の会場開催では50名程度だった参加者が、ライブ配信に切り替えることで300名を超えるようになったという事例もあります。
また、時差の関係で参加が困難だった海外の顧客や取引先にも情報を届けることができるため、グローバル展開を進める企業にとっては特に価値の高い手法と言えるでしょう。
コンテンツが資産として再利用できる(アーカイブ活用)
ライブ配信の内容は録画・保存でき、後から何度でも視聴することができます。新入社員研修や商品説明資料として再利用したり、見逃した人への配慮としてアーカイブ配信を行ったりと、一度作成したコンテンツを有効活用できるのも魅力です。
特に研修コンテンツとしての再利用価値は非常に高く、一度質の高いライブ配信研修を作成すれば、新入社員が入社するたびに繰り返し活用できます。講師のスケジュール調整や会場確保の必要がないため、研修の実施頻度を上げることも可能になります。
また、アーカイブされたコンテンツは、SEO(検索エンジン最適化)の観点からも価値があります。適切なタイトルや説明文を付けてYouTubeなどにアップロードすることで、継続的に新規顧客の獲得につなげることができるのです。
ブランド信頼性・透明性の向上
ライブ配信では、台本通りではない自然な会話や反応を見せることができるため、企業の人柄や価値観が伝わりやすくなります。これにより、ブランドの信頼性や透明性を高めることができ、顧客からの好感度向上にもつながります。
特に昨今、消費者は企業の「顔が見える」コミュニケーションを重視する傾向が強くなっています。SNSの普及により、企業も一人の人格として捉えられることが多くなり、親しみやすさや信頼性がより重要な要素になってきているのです。
ライブ配信では、予期しない質問に対する自然な反応や、配信中の小さなハプニングへの対応など、「生の人間らしさ」が伝わりやすいため、視聴者との距離感を大幅に縮めることができます。これは録画された動画コンテンツでは決して実現できない、ライブ配信独自の価値と言えるでしょう。
企業のライブ配信活用シーン【事例付】
実際に企業ではどのような場面でライブ配信が活用されているのでしょうか。具体的な事例とともに、それぞれの活用シーンの特徴やポイントをご紹介していきます。
セミナー・ウェビナー
専門知識を持つ社員が講師となり、業界の最新動向や技術情報を配信するセミナーは、ライブ配信活用の代表例です。参加者からの質問にリアルタイムで答えることで、より深い学びを提供できます。
ウェビナー形式のライブ配信では、プレゼンテーション資料を画面共有しながら、講師が解説を行います。通常の対面セミナーと違い、参加者は顔を見せる必要がないため、気軽に質問しやすい環境が作れるのも大きなメリットです。
また、チャット機能を活用して、参加者同士の意見交換を促すことも可能です。これにより、単なる一方向の情報提供ではなく、参加者全員で学び合うコミュニティ的な雰囲気を作り出すことができます。
事例
成功事例 IT企業のA社では、毎月1回の技術セミナーをライブ配信で開催。従来の会場開催では50名程度の参加者でしたが、ライブ配信により300名以上の参加者を獲得し、リード創出数も3倍に増加しました。特に、録画したセミナー動画を後日YouTube にアップロードすることで、継続的な集客効果も実現しています。
採用活動(説明会・社内紹介)
会社説明会や社内見学をライブ配信で行うことで、より多くの求職者に企業の魅力を伝えることができます。実際に働く社員の様子や職場の雰囲気を生で見せることで、求職者の不安を解消できるのも大きなメリットです。
特に効果的なのは、現場社員との質疑応答セッションです。人事担当者では答えにくい「実際の働きやすさ」や「キャリアパス」について、現場で働く先輩社員が率直に答えることで、求職者にとって非常に有益な情報提供ができます。
また、オフィス見学をライブ配信で行う「バーチャルオフィスツアー」も人気が高まっています。カメラを片手にオフィス内を歩きながら、各部署の紹介や働く環境の説明を行うことで、実際に訪問したかのような体験を提供できます。。
事例
ある精密機器メーカーでは、工場見学をライブ配信で実施。カメラを持って工場内を歩きながら、製造工程や働く社員の姿を配信した結果、従来の工場見学会よりも2倍多い応募者を獲得することができました。特に理系学生からの応募が大幅に増加し、採用活動の効率化にも成功しています。
社内イベント・研修
全社会議や研修をライブ配信で行うことで、拠点が分散している企業でも全員が同じ情報を共有できます。録画しておけば、参加できなかった社員も後から視聴できるため、情報共有の漏れを防ぐことができます。
特に有効なのは、経営陣からの重要な発表や、新しい方針・戦略の共有です。ライブ配信により、全社員が同じタイミングで同じ情報を受け取ることができ、組織全体の一体感を高めることができます。
また、外部講師を招いた研修では、複数の拠点に同時に配信することで、講師の交通費や宿泊費を大幅に削減しながら、全社員に質の高い研修を提供することが可能になります。
事例
全国展開している金融サービス企業では、四半期ごとの全社会議をライブ配信で実施。移動コストを年間約500万円削減しながら、全社員の参加率を95%以上に向上させることができました。また、海外拠点の社員も参加しやすくなり、グローバルな情報共有体制を構築できています。
ライブコマース(商品販売)
商品の特徴や使い方をライブ配信で説明しながら、その場で購入できるライブコマースも注目されています。視聴者の質問にリアルタイムで答えることで、購入への不安を解消し、コンバージョン率の向上が期待できます。
ライブコマースの最大の魅力は、商品の「実際の使用感」を伝えられることです。テキストや写真だけでは伝わりにくい質感、サイズ感、使い心地などを、リアルタイムでデモンストレーションすることで、視聴者の購買意欲を大きく高めることができます。
また、「今だけ限定価格」や「配信中のみの特典」など、ライブ配信ならではの特別感を演出することで、その場での購買行動を促進することも可能です。
事例
オーガニックコスメブランドでは、新商品のライブ配信販売を実施。メイクアップアーティストが実際に商品を使いながら解説し、視聴者からのメイクに関する質問にもリアルタイムで答えることで、1回の配信で通常の3倍の売上を記録しました。特に、配信中に寄せられた質問から新商品開発のヒントも得られ、マーケティングリサーチとしての価値も実感しています。
カンファレンス・展示会のオンライン化
大規模なカンファレンスや展示会も、ライブ配信を活用してオンライン開催することが可能です。複数のセッションを同時配信したり、バーチャル展示ブースを設けたりと、リアルイベントに近い体験を提供できます。
オンライン展示会では、各企業のブースをライブ配信で紹介し、来場者が興味のあるブースの配信を選んで視聴することができます。チャット機能を活用すれば、その場で商談のアポイントメントを取ることも可能です。
また、基調講演やパネルディスカッションなどの主要コンテンツをライブ配信することで、会場に来られない人にも価値のある情報を提供できます。録画したコンテンツは後日オンデマンドで配信することで、より多くの人にリーチすることも可能です。
事例
業界団体では、年次カンファレンスをハイブリッド開催(現地参加とオンライン参加の併用)に変更。現地参加者150名、オンライン参加者800名の合計950名が参加し、従来の2倍以上の参加者を獲得しました。参加費も従来の半額に設定できたため、参加者の満足度も大幅に向上しています。
企業ライブ配信を成功させるコツ
ライブ配信を成功させるためには、いくつかのポイントを押さえる必要があります。実際の導入前に確認しておきたいコツをご紹介します。
ターゲットと目的を明確にする
「誰に」「何を」伝えたいのかを明確にすることが最も重要です。ターゲット層の興味や視聴習慣を理解し、それに合わせた内容や配信時間を設定しましょう。目的があいまいだと、視聴者にとって価値のないコンテンツになってしまいます。
例えば、新規顧客獲得が目的なら、商品の魅力を分かりやすく伝える内容にし、既存顧客向けなら、より深い活用方法や業界動向について扱うなど、内容を明確に分ける必要があります。
また、ターゲット層の年齢や職業によって、好まれる配信スタイルも大きく異なります。若い世代向けならカジュアルで親しみやすい雰囲気、経営層向けなら専門的で信頼感のある内容というように、雰囲気作りも重要な要素です。
適切なプラットフォームやツールを選ぶ
ターゲット層がよく利用するプラットフォームを選ぶことが大切です。BtoB企業なら LinkedIn Live、若い世代がターゲットなら Instagram Live や TikTok Live、主婦層なら YouTube Live など、目的に応じて最適なプラットフォームは大きく変わります。
また、参加者数や配信品質、必要な機能(チャット、画面共有、録画など)によっても選択肢は変わってきます。無料のプラットフォームから始めて、必要に応じて有料の専用ツールに移行するという段階的なアプローチもおすすめです。
さらに、複数のプラットフォームで同時配信を行う「マルチ配信」も効果的です。それぞれのプラットフォームの特性を活かして、より多くの視聴者にリーチできます。
機材・環境を整えてトラブルを防ぐ
音声や映像の品質は視聴者の満足度に直結します。最低限、安定したインターネット環境と音声が聞き取りやすいマイクは用意しましょう。事前のテスト配信を行い、トラブル時の対応策も準備しておくことが重要です。
特に音声品質は非常に重要で、映像が多少荒くても我慢できますが、音声が聞き取りにくいと視聴者はすぐに離脱してしまいます。外部マイクの使用や、配信環境の防音対策も検討しましょう。
照明についても、顔がはっきりと見える明るさを確保することが大切です。自然光を活用したり、簡易的な照明機材を導入したりすることで、プロフェッショナルな印象を与えることができます。
推奨される機材としては、高品質なウェブカメラまたはビデオカメラ、外部マイクとしてピンマイクやUSBマイク、安定したインターネット接続では有線接続が推奨されます。また、照明機材としてリングライトなどの導入や、予備のバッテリーや充電器の準備も重要です。
視聴者が参加しやすい時間帯を選ぶ
ターゲット層のライフスタイルに合わせた時間帯を選びましょう。会社員向けなら平日の夜や土日、主婦層向けなら平日の午前中、学生向けなら夕方以降など、視聴者の都合を考慮した時間設定が参加率向上のカギになります。
また、時間帯だけでなく配信時間の長さも重要です。内容によって適切な長さは変わりますが、一般的にはライブ配信の集中力が続くのは60〜90分程度とされています。長時間になる場合は、適度に休憩時間を設けることも大切です。
さらに、海外の視聴者も対象にする場合は、時差を考慮した時間設定や、複数回の配信を検討する必要があります。
定期的な配信で習慣化・ファン化を促進する
単発の配信よりも、定期的な配信の方が視聴者の習慣として定着しやすくなります。「毎週金曜日の17時から」など、決まった時間に配信することで、視聴者にとって楽しみな時間になり、ファン化を促進できます。
インタラクション(コメント・Q&A)を活かす
単発の配信よりも、定期的な配信の方が視聴者の習慣として定着しやすくなります。「毎週金曜日の17時から」「毎月第3木曜日の12時から」など、決まった時間に配信することで、視聴者にとって楽しみな時間になり、ファン化を促進できます。
定期配信を行う場合は、継続できる範囲でスケジュールを組むことが重要です。無理な頻度で始めて途中で継続できなくなると、せっかく獲得したファンを失ってしまう可能性があります。
また、シリーズ化することで、視聴者の継続視聴を促進することも可能です。「全6回の技術講座」や「月替わり商品紹介」など、次回への期待感を持たせる構成にすると効果的です。
企業ライブ配信の注意点
企業がライブ配信を行う際に気をつけるべきポイントもいくつかあります。トラブルを避けるために、事前に確認しておくべき重要な注意点をご紹介します。
個人情報や社外秘データの取り扱い
ライブ配信では、意図せず個人情報や機密情報が映り込んでしまう可能性があります。配信前には画面に映る範囲をしっかりチェックし、必要に応じて背景を変更したり、資料にモザイクをかけたりする準備をしておきましょう。
特に注意が必要なのは、パソコン画面の共有時です。デスクトップに機密ファイルのショートカットがあったり、通知で個人情報が表示されたりする可能性があります。配信専用のアカウントを作成したり、仮想背景を使用したりすることで、リスクを最小限に抑えることができます。
また、参加者の顔や名前が映り込む場合は、事前に同意を得ておくことが重要です。社内配信であっても、録画・公開される可能性がある場合は、参加者への事前説明を怠らないようにしましょう。
著作権・音楽利用のルール
BGMや効果音を使用する際は、著作権に注意が必要です。商用利用可能な楽曲や、企業が利用許諾を得た楽曲のみを使用しましょう。知らないうちに著作権侵害になってしまうケースもあるので、事前の確認が大切です。
YouTubeやInstagram、TikTokなどのプラットフォームでは、著作権侵害があると自動的に配信が停止されたり、音声がミュートされたりする機能があります。これにより配信が中断してしまうと、視聴者の満足度が大きく下がってしまう可能性があります。
安全策として、著作権フリーの音楽ライブラリを活用したり、自社で音楽を制作したりすることをおすすめします。また、配信中に外部の音楽が流れ込まないよう、周囲の環境にも注意を払いましょう。
生配信ならではのトラブル対策
インターネット接続の不安定化や機材の故障など、生配信特有のトラブルが発生する可能性があります。予備の機材を準備したり、トラブル時の対応フローを作成したりして、万が一の際にも冷静に対処できるよう準備しておきましょう。
想定すべきトラブルには、インターネット接続の不安定化、カメラやマイクの故障、配信ソフトのクラッシュ、停電やPCの故障、背景音の侵入、配信者の体調不良などがあります。
これらのトラブルに備えて、事前にバックアッププランを用意しておくことが重要です。例えば、メイン配信者が急遽参加できなくなった場合の代役や、技術的トラブル時の視聴者への告知方法などを決めておきましょう。
また、トラブル発生時は慌てずに視聴者に状況を説明し、解決に向けた対応を透明性を持って伝えることで、むしろ企業への信頼を高めることもできます。
視聴者離脱を防ぐコンテンツ設計
長時間の配信では視聴者が途中で離脱してしまう可能性があります。適度な休憩を入れたり、インタラクティブな要素を盛り込んだりして、最後まで飽きずに視聴してもらえる工夫を心がけましょう。
視聴者維持に効果的なテクニックとしては、冒頭で配信全体の流れを説明すること、15〜20分ごとに小休憩やまとめの時間を設けること、クイズやアンケートなど参加型コンテンツを挟むこと、重要なポイントは繰り返し説明すること、視聴者のコメントを積極的に取り上げること、次回予告や限定情報で配信最後まで引きつけることなどがあります。
特に企業の配信では、専門的な内容になりがちですが、視聴者のレベルに合わせて分かりやすい言葉で説明したり、具体例を多く使ったりすることで、離脱率を下げることができます。
導入を検討する企業におすすめのライブ配信サービス
ライブ配信を始めたいけれど、どのサービスを選べばよいのか迷っている企業の方も多いでしょう。用途別におすすめのサービスを、それぞれの特徴や価格帯も含めて詳しくご紹介します。
導入しやすい国産ツール
初めてライブ配信を導入する企業には、日本語サポートが充実している国産ツールがおすすめです。操作が直感的で、トラブル時のサポートも日本語で受けられるため、安心して利用できます。
おすすめの国産ツールとしては、企業向けライブ配信に特化したサービスでセキュリティ面も安心なネクプロ、簡単操作でプロ品質の配信が可能で録画機能も充実したmillvi、大手企業での導入実績が豊富で安定性に定評のあるJ-Streamなどがあります。
これらのツールは、初期設定から運用まで手厚いサポートを受けられるため、社内にITスキルの高いスタッフがいない企業でも安心して導入できます。
大規模イベントに対応できるサービス
数百人から数千人規模の視聴者を想定している場合は、大規模配信に対応したプラットフォームを選ぶ必要があります。同時接続数の制限や配信品質の安定性を事前に確認しておきましょう。
大規模配信対応サービスには、無料で大規模配信が可能で録画・アーカイブ機能も充実したYouTube Live、企業ページからの配信でブランディング効果も期待できるFacebook Live、ウェビナーに特化した機能で企業イベントに最適なZoom Webinar、Office 365との連携でスムーズな運用が可能なMicrosoft Teams Live Eventsなどがあります。
これらのサービスでは、万人規模の同時視聴にも対応できる安定した配信基盤を提供しています。ただし、大規模配信では事前のテストがより重要になるため、本番前の入念な準備が必要です。
コマース機能に強いプラットフォーム
商品販売を目的としたライブ配信を行う場合は、決済機能が充実しているプラットフォームを選ぶことが重要です。視聴者が配信中にスムーズに購入できる仕組みが整っているかをチェックしましょう。
ライブコマース対応サービスには、Instagram内で商品購入まで完結できるInstagram Shopping、若年層に人気の高いプラットフォームであるTikTok LIVE Shopping、商品紹介動画から直接購入ページへ誘導できるYouTube Shopping、ライブコマースに特化した機能が充実している17LIVEなどがあります。
これらのプラットフォームでは、配信中に商品情報を表示したり、ワンクリックで購入できたりする機能が提供されています。ただし、プラットフォームごとに手数料や利用条件が異なるため、事前の確認が必要です。
まとめ|ライブ配信は企業の成長ドライバーになる
いかがでしたでしょうか?ライブ配信の可能性から具体的な活用方法まで、幅広くご紹介してきました。
今回の重要なポイント
- コスト効率の良いマーケティング手法:会場費や交通費を大幅に削減しながら、より多くの人にリーチできる
- 双方向コミュニケーションの実現:リアルタイムでの質疑応答により、顧客との信頼関係を深められる
- 多様な活用シーン:セミナー、採用活動、社内研修、ライブコマースまで幅広い用途で活用可能
- アーカイブ活用による資産化:一度の配信コンテンツを研修資料などに再利用でき、長期的な価値を生み出す
- ブランド透明性の向上:自然な会話や反応を通じて、企業の人柄や価値観を効果的に伝えられる
ライブ配信は、もはや単なる「新しい技術」ではありません。顧客との距離を縮め、ブランド価値を高める重要な戦略ツールとして、多くの企業で成果を上げています。
特にコロナ以降、オンラインでのコミュニケーションが当たり前になった今、ライブ配信を活用できるかどうかが企業の競争力を左右する時代になってきています。
まずは小さなセミナーや社内イベントからスタートして、徐々に活用範囲を広げていくのがおすすめです。今回の記事を参考に、ぜひあなたの会社でもライブ配信の導入を検討してみてください!