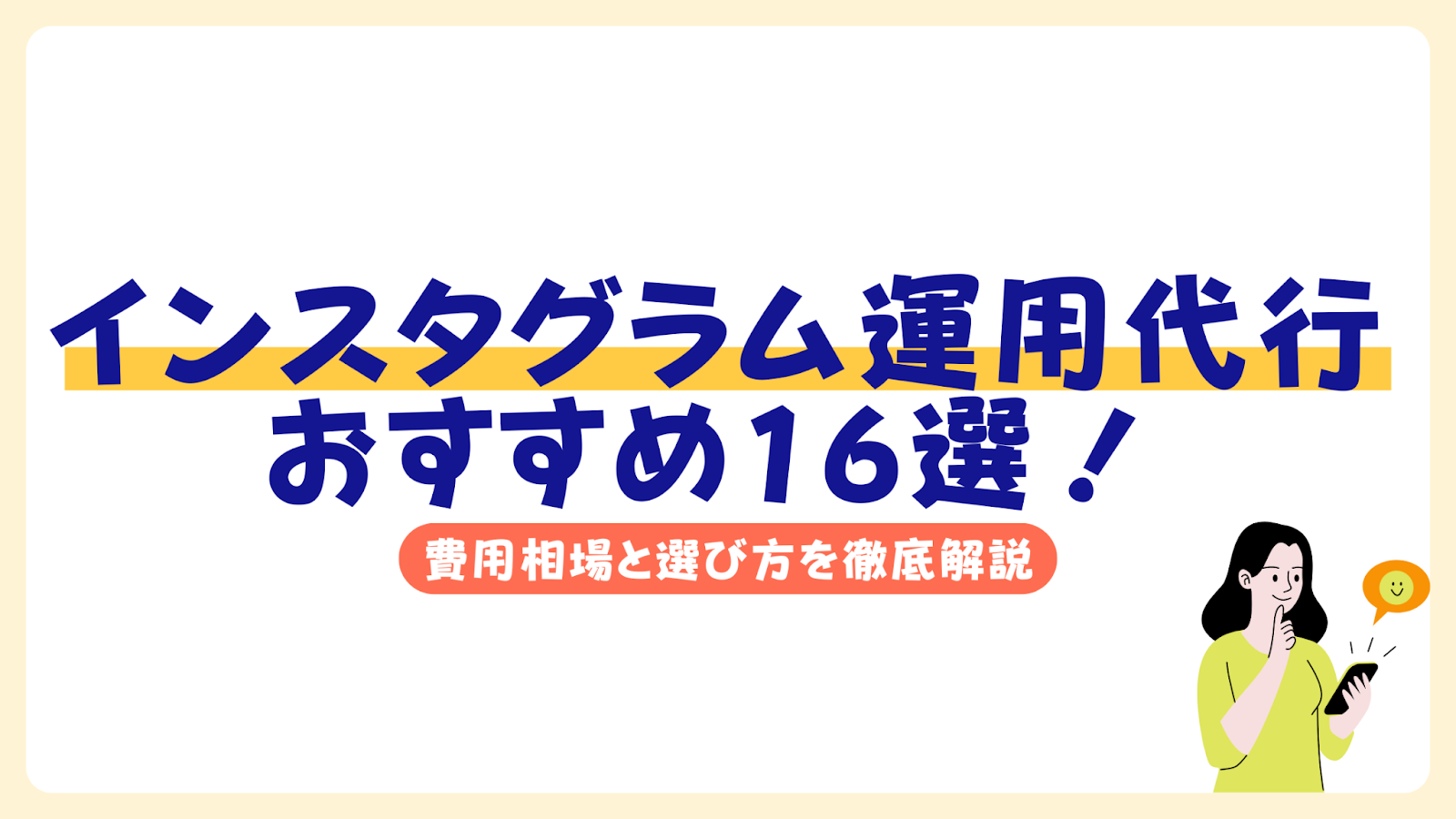【徹底比較】YouTube運用は内製と外注どっちが良い?費用・効果・メリットを解説

YouTube運用を始めたいけれど、「自社でやるべきか?それとも外注すべきか?」と悩む方は多いはずです。
どちらがお得で効果的なのか、判断に迷ってしまいますよね。
そこで今回は、YouTube運用の内製と外注の違いを分かりやすく解説し、それぞれのメリット・デメリット、そして最適な選び方をご紹介します。

東京大学卒業後、金融機関、スタートアップベンチャーを経て2016年にサイバーエージェントに入社してインターネット広告事業に従事した後、2020年7月に独立しました。
特に広告領域においてはプランニングから運用まで幅広く携わり、ナレッジは日本トップレベルだと自負しています。
◆ 経歴
2014:東京大学行動文化学科 卒業
2014:住友生命保険相互会社 入社
2015:株式会社RoseauPensant 入社
2016:株式会社サイバーエージェント 入社
2020:株式会社CYANd 創業/代表取締役就任
2022:株式会社Minato 入社/広告事業責任者就任
YouTube運用の重要性とは?
最近では個人の収益手段としても、企業の集客・ブランディング手段としても、YouTubeの活用が注目されています。特に日本国内では毎月6,900万人ものユーザーが利用しており、幅広い世代にリーチできる強力な媒体です。
YouTubeの大きな魅力は、他のSNSにはないストック型メディアという点です。一般的なSNSはアップロードした後すぐに流れていってしまうのに対し、YouTubeは検索や関連動画から長期的に視聴され続けます。そのため、質の高いコンテンツを積み上げていくことで、資産価値のあるチャンネルを構築できるのです。
また、動画はテキストや画像に比べて圧倒的に多くの情報を届けられるため、商品の魅力やブランドの世界観をストーリーとして訴求できるという面でも企業にとってメリットがあります。
ただし、これらの魅力を最大限活かすには適切な運用が欠かせません。そこで重要になるのが、自社で運用する「内製」か、外部に依頼する「外注」かの選択です。
YouTube運用の方法は「内製」と「外注」の2つ
YouTube運用には大きく分けて2つのアプローチがあります。
まず内製とは、企画から撮影、編集、アップロード、分析まですべて自前で行う運用方法です。個人なら一人または仲間とチーム、企業ならマーケティング担当者や広報部がチームを組んで、撮影機材や編集ソフトも自前で購入しながら進めていくスタイルになります。
一方、外注とはYouTube運用の一部または全部を専門会社や個人に依頼する方法です。依頼内容は幅広く、動画撮影のみや台本制作のみといった部分的なものから、企画立案から分析まで全てお任せするパターンまで様々です。最近では、サムネイルやタイトル設計といった細かい業務やSEO対策に特化したサービスも増えています。
つまり、YouTube運用における内製と外注の違いは、誰が制作や運営を行うのかということ。自前で進めるか、外部の専門家を活用するかによって、取り組み方や成果の出方が大きく変わってくるのです。
内製でYouTube運用するメリット・デメリット
内製でYouTube運用を行う最大のメリットは、圧倒的な柔軟性の高さです。外部とのスケジュール調整が不要なため、急な告知や方針変更にも即座に対応できます。思いついたアイデアをすぐに形にできるスピード感は、外注ではなかなか実現できない魅力ですね。
また、コスト面でも大きなメリットがあります。外部に依頼すると企画段階から費用が発生し、編集まで依頼すると数十万円の費用がかかることも珍しくありません。内製なら機材やソフトへの初期投資は必要ですが、動画を作れば作るほど1本あたりのコストは安くなっていきます。
さらに、内容の理解度が深い点も見逃せません。個人なら自分のキャラクターや世界観をダイレクトに表現でき、企業なら自社サービスを熟知しているからこそ作れる、ちぐはぐにならないコンテンツを提供できます。
しかし、内製にはデメリットもあります。一番大きいのは、能力や人手の不足です。体系的な訓練や経験を持たないため、企画力や撮影スキル、編集テクニックに限界があります。さらに、スキルを持っていても本業で手いっぱいになってしまい、十分な時間を割けないという現実的な問題もあります。
専門性の限界も課題です。どうしてもプロの業者に比べるとノウハウが乏しいため、動画のクオリティにばらつきが出やすく、視聴者にインパクトを与えにくいコンテンツになってしまうことも多いのが実情です。
外注でYouTube運用するメリット・デメリット
外注の一番のメリットは、専門性の高さです。YouTubeのアルゴリズムやトレンドに精通し、視聴者心理を理解した企画や動画制作を行えるため、成果につながりやすいコンテンツを作ることができます。自前のノウハウがなくても、外注することで一気に専門的なYouTube運用が可能になるのです。
また、効率の良さも大きな魅力です。企画から分析までの作業を外部に任せることで、自分は得意分野に集中したり、本業に専念したりできます。時間的制約の解消や人的労力の削減によって、他の重要な業務に集中できるのは経営的にも大きなメリットといえるでしょう。
さらに、即効性も期待できます。最適化された制作プロセスやバズるポイントを熟知したプロが手がけるため、内製では時間のかかる成果を短期間で出せる可能性が高くなります。
一方で、外注にはデメリットもあります。まず、コストが大きな負担となります。ワンポイントの外注でも1万円程度は必要で、企画から運用全般を依頼すると月額数十万円の費用が発生することも珍しくありません。予算に余裕がない場合は、大きな負担となってしまいます。
また、方針のずれが生まれやすい点も注意が必要です。自分の想定とは異なる動画企画が提案されたり、やりたいことと外注先の得意分野にギャップがあったりすることで、理想とは違う方向に進んでしまうリスクがあります。
最後に、依存のリスクも考慮すべき点です。運用を丸ごと外注してしまうと、自前のノウハウが蓄積されにくく、将来的に自分たちだけで継続するのが難しくなってしまう可能性があります。
失敗しないYouTube運用の選び方
YouTube運用を成功させるポイントは、自分たちの状況を正しく把握することです。すべてのケースで「絶対にこちらが良い」とは言えないため、以下の観点で検討することが重要になります。
まず最初に取り組みたいのが、自社リソースの整理です。技術力、人手、時間、予算の4つの観点から、現在の状況を客観視してみましょう。動画制作に必要なスキルをどの程度持っているか、YouTube運用に携われる人がどれだけいるか、どれだけの時間を割けるか、機材費用や外注費用の予算はどの程度あるかを明確にすることで、内製と外注のどちらが向いているかが見えてきます。
次に重要なのが、結果をどのタイミングで出したいかということです。すぐに成果を求めているなら、外注で専門的な企画を依頼する方が効果的です。一方で、将来的なノウハウの蓄積を重視し、長期的に自社で運営できるようになりたいなら、内製でじっくり取り組む方が良いでしょう。
ただし、内製か外注かの二択にこだわる必要はありません。
ハイブリッド運用という選択肢もおすすめです。例えば、企画や撮影は自前で行い、編集や分析は外注するといった方法なら、質の高いコンテンツを提供しながらもノウハウを蓄積できます。最初は外注でプロのやり方を学び、徐々に内製化していくという段階的なアプローチも効果的です。
まとめ:自社に合ったYouTube運用を選ぼう
YouTube運用には、内製なら柔軟性、外注なら効率性という特徴があります。
内製では自分たちの理解度の高さを活かし、スピード感や独自性のある発信が可能ですが、時間的制約や人手不足、スキル面での限界が課題となります。一方、外注は専門知識を活用して効率的に成果を出せる反面、コストや方針のずれといった制約が生じます。
最適な方法は個々の状況によって異なりますが、まずは小さく内製から始め、成果や課題を見極めながら必要に応じて外注を取り入れるのが安心です。状況に応じて両者を組み合わせ、自社に合った運用スタイルを築くことが成功への近道となるでしょう。