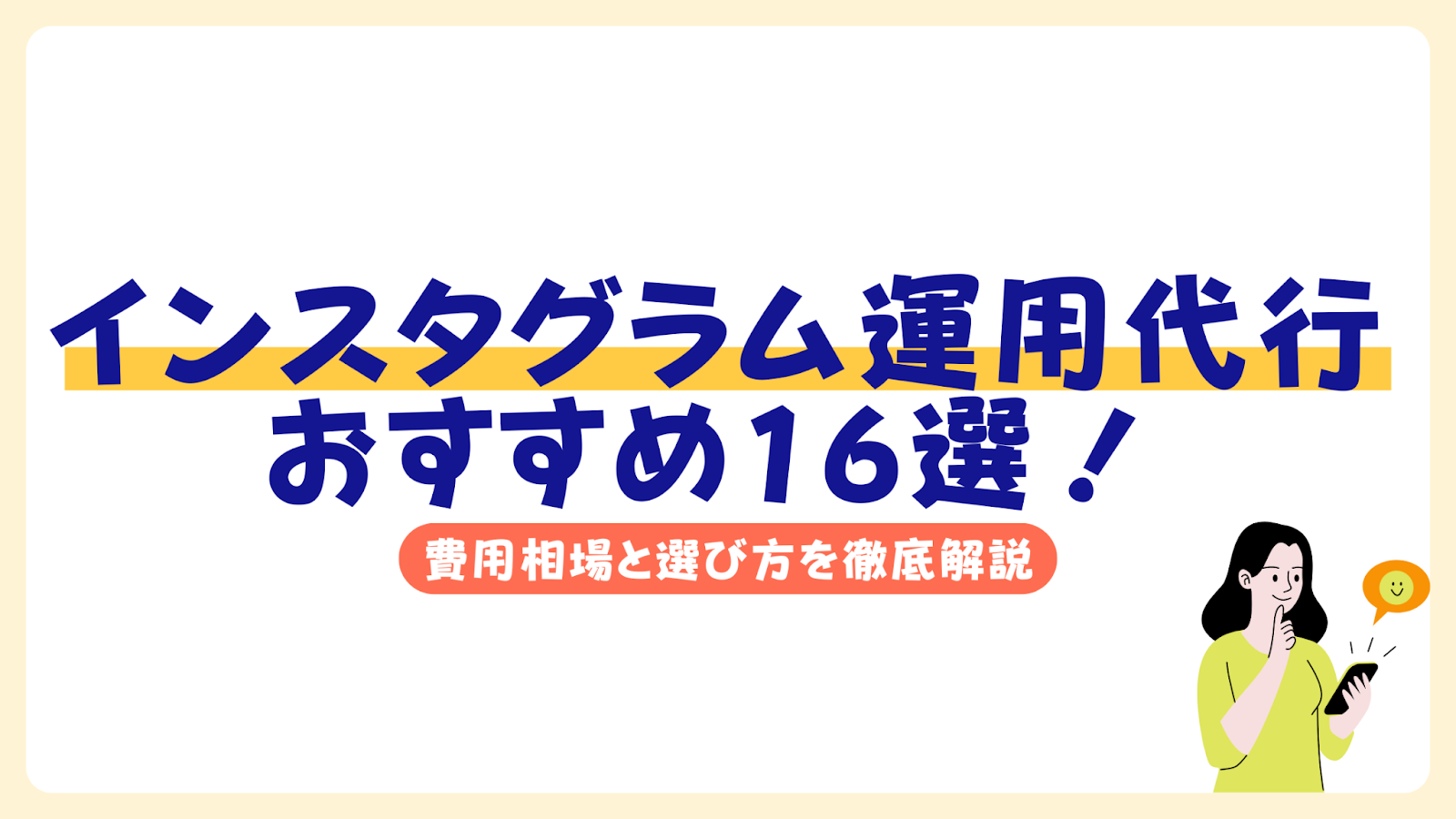【保存版】YouTube運用で成果が出ない理由はコレ|失敗パターン5選と勝ち筋ロードマップ

YouTube運用を始めたものの、チャンネル登録者数や再生回数がなかなか伸びずに悩んでいる企業担当者の方も多いのではないでしょうか。実際に、多くの企業がYouTube運用で失敗を経験し、期待した成果を得られずに運用を断念してしまうケースが後を絶ちません。
本記事では、YouTube運用で失敗する企業に共通する5つの致命的なミスと、それぞれの具体的な改善策について詳しく解説します。これからYouTube運用を始める方も、既に運用中で成果が出ていない方も、ぜひ参考にしてください。

東京大学卒業後、金融機関、スタートアップベンチャーを経て2016年にサイバーエージェントに入社してインターネット広告事業に従事した後、2020年7月に独立しました。
特に広告領域においてはプランニングから運用まで幅広く携わり、ナレッジは日本トップレベルだと自負しています。
◆ 経歴
2014:東京大学行動文化学科 卒業
2014:住友生命保険相互会社 入社
2015:株式会社RoseauPensant 入社
2016:株式会社サイバーエージェント 入社
2020:株式会社CYANd 創業/代表取締役就任
2022:株式会社Minato 入社/広告事業責任者就任
YouTube運用で失敗する企業の5つの共通パターン
YouTube運用に失敗する企業には、明確な共通点があります。ここでは、特に陥りやすい失敗パターンを重要度順にランキング形式でご紹介します。
第5位:バズることだけを目指して運用している
多くの企業がYouTube運用失敗の要因として、「再生数を稼がなければならない、バズが必要だ」と考えてしまうことが挙げられます。動画がバズを生み出せば多くの人の目に触れるため、認知向上に繋がって結果が出ると予想する担当者は多いのが現状です。
しかし、瞬間的なバズでは不特定多数の目に留まっても記憶には残りにくく、そもそもバズ自体が狙って何度も生み出せるものではありません。特に企業のYouTube運用においては、バズよりも将来の見込み顧客候補の目に留まることが重要です。
改善策
- バズよりも将来の見込み顧客候補を獲得することが重要だと認識する
- 見込み顧客候補に役立つ情報を届けることを意識し、動画を制作する
- 適切なアクションを促すような情報を届ける
そもそも、YouTube運用の目的はバズを生み出すことではありません。動画を通してブランディングをしたり問い合わせに繋げたりすることが、本来の目的のはずです。見込み顧客候補となる層を惹きつけるような動画を制作できているかどうか、改めて分析してみましょう。
第4位:運用体制を整えずに始めてしまう
YouTube運用失敗の大きな要因として、運用体制の不備が挙げられます。企業がYouTubeアカウントを運用する場合、InstagramやTwitterに比べると運用の負荷が大きく、通常の業務と並行して片手間にはできません。
動画撮影から始まり、動画編集やアップロード、視聴維持率の解析など、YouTube運用には多くの作業が伴います。体制を整えずに始めてしまうと、YouTube運用に関わる業務が担当者の大きな負担にもなりやすく、結果が出る前に挫折してしまう可能性が大きくなります。
改善策
- 経営者やマーケティングのトップがYouTubeの運用は他のSNSよりも負荷が大きいことを認識する
- 動画編集やキャスティング、アップロードなどの作業を行うチーム体制を整える
- チーム体制を整えることが難しければ、外部への委託も検討する
企業のYouTube運用を成功させるためには、動画のクオリティはもちろん、コンスタントな動画更新も重要です。そのため、継続的に更新していくには、やはりチーム体制を整えて運用するべきでしょう。
第3位:動画投稿後の分析・改善を怠っている
YouTube運用失敗の主要な原因として、動画を投稿して終わりになってしまうことが挙げられます。YouTubeは企画作成や動画編集、キャスティングといった作業数も多く、アップロードしたら満足してしまう担当者の方は多いのではないでしょうか。
しかし、YouTube運用を成功させる上で、結果に繋げるために重要なポイントは、アップロード後の解析と改善です。YouTubeは企業がユーザーとダイレクトにコネクトできるプラットフォームであり、視聴維持率やサムネイルクリック数などの数値からユーザーの満足度も分かります。
改善策
- アップロードがゴールではなく、分析・改善が最も重要なステップと認識する
- 反応が良かった動画と悪かった動画を数値に基づいてそれぞれの原因を分析する
- YouTubeアナリティクスを利用して数値データから分析し、さらに再現性を高める
YouTube運用の成功をコミットしたいのであれば、YouTubeアナリティクスからデータを分析し、企画内容の改善に繋げるというステップは避けられません。YouTubeアナリティクスを活用しながら、ユーザーから自社のチャンネルや動画がどのように評価されているのか日々チェックしましょう。
第2位:短期的な結果を求めすぎる
YouTube運用失敗の大きな要因として、短期的に結果を求めすぎることが挙げられます。「今から始めれば、再生回数や登録者数がどんどん増えて結果もすぐに出るだろう」と思っている担当者は多いのが現状です。
しかし、短期間でチャンネルが伸びることはほとんどありません。成功しているチャンネルでも、運用開始から約9ヵ月間はほとんど登録者がいない状況が続くことは珍しくありません。結果が出るまでは2~3年ほどかかり、長期戦になることがほとんどです。
特に初期の頃は実績がない状態なので、露出も少なくなかなか結果に反映されません。
改善策
- 運用を始めてしばらくは結果が出ないものと認識しておく
- 経営陣やマーケティング部門のトップが2、3年はかかると見据えた上で、しっかりとスポンサーになって取り組む
- 運用開始直後は特に、量に重きを置いて実績数を増やすことに注力する
YouTube運用で失敗を避けるためには、長期的な視点が不可欠です。ここで挫折せずに続けてしっかりと立ち上げることで、Pull型営業の仕組みが出来上がり、YouTubeが強力な営業チャネルへ育ちます。
第1位:企業視点の自己満足コンテンツを作っている
YouTube運用失敗の最も大きな要因として、「企業側の伝えたいことばかりを詰め込んでしまう」ということが挙げられます。これは最も陥りやすく、かつ最も致命的な失敗パターンです。
自社の商品やサービスの紹介ばかり詰め込んだ内容だと、視聴者はつまらないと感じて離脱するため、視聴維持率が下がっていきます。さらには、YouTubeからもユーザーに必要のない動画と判断され、結果が出ないという悪循環に陥ってしまいます。
成功事例を見ると、エンタメ性を重視し、アニメーションでエンタメ性を盛り込んだことで、視聴者が興味を持てるような内容に仕上げており、89万回を超える再生数を記録した企業もあります。
改善策
- エンタメ性を重視し、ユーザーの興味関心を惹きつけることが最重要
- ユーザーが視聴するメリットのある内容を盛り込む
- ユーザーは広告と判断すると離脱するので、企業色はできるだけ抑える
ユーザーは面白い動画や、知識やノウハウが学べるような動画などを求めているのであって、企業の広告が見たいわけではありません。YouTube運用で失敗を避けるためには、ユーザーの興味を惹きつける動画を制作しているか一度振り返ってみることが重要です。
YouTube運用失敗を避けるための具体的な改善ステップ
YouTube運用の失敗を避けるために、以下の具体的なステップを踏むことをおすすめします。
運用目的の明確化と目標設定
YouTube運用失敗を防ぐためには、まず運用目的を明確にすることが重要です。ブランディング、リード獲得、売上向上など、具体的な目標を設定し、それに基づいたKPIを決めましょう。
目的が曖昧だと、コンテンツの方向性もブレてしまい、結果として視聴者にとって価値のない動画を量産してしまう可能性があります。
ターゲットユーザーの詳細なペルソナ設定
YouTube運用で失敗しないためには、ターゲットユーザーのペルソナを詳細に設定することが不可欠です。年齢、性別、職業、興味関心、普段の情報収集方法など、できるだけ具体的に設定しましょう。
ペルソナが明確になることで、どのようなコンテンツが刺さるのか、どのような表現が効果的なのかが見えてきます。
競合チャンネルの徹底分析
同業他社や類似業界の成功しているYouTubeチャンネルを分析することで、失敗を避けるヒントを得ることができます。どのような企画が人気なのか、どのような表現を使っているのか、投稿頻度はどの程度なのかを調査しましょう。
ただし、完全にコピーするのではなく、自社独自の価値を提供できる差別化ポイントを見つけることが重要です。
継続的な分析と改善サイクルの構築
YouTube運用失敗を避けるためには、継続的なPDCAサイクルの構築が不可欠です。YouTubeアナリティクスを活用して、以下の指標を定期的にチェックしましょう:
- 視聴維持率
- クリック率
- エンゲージメント率
- チャンネル登録率
- 流入経路
これらのデータを基に、何が良くて何が悪かったのかを分析し、次の動画制作に活かしていくことが成功への近道です。
YouTube運用失敗事例から学ぶ教訓
実際のYouTube運用失敗事例から学べる教訓をいくつかご紹介します。
事例1:商品紹介動画ばかりで視聴者が離脱
ある企業では、自社商品の機能や特徴を紹介する動画ばかりを投稿していました。しかし、視聴者にとっては広告のような内容で、視聴維持率は10%以下という結果に。
この失敗から学んだ教訓は、商品紹介よりも「その商品を使ってどのような課題が解決できるのか」「実際に使っている人の体験談」など、視聴者にとって価値のある情報を提供することの重要性でした。
事例2:一人の担当者に全てを任せて挫折
別の企業では、一人のマーケティング担当者にYouTube運用の全てを任せていました。企画、撮影、編集、分析まで一人で行っていたため、クオリティが低下し、更新頻度も月1回程度まで減少してしまいました。
この失敗から、YouTube運用には専門チームが必要であることを学び、外部の制作会社と連携することで運用を立て直すことができました。
事例3:短期的な成果を求めて方向性を頻繁に変更
ある企業では、3ヶ月経っても目立った成果が出ないことに焦り、コンテンツの方向性を頻繁に変更しました。教育系コンテンツから始まって、エンタメ系、ニュース解説系と次々と変更した結果、チャンネルの一貫性がなくなり、固定ファンを獲得することができませんでした。
この失敗から、一定期間は同じ方向性で継続することの重要性を学び、最低でも半年から1年間は同じコンセプトで運用を続けることを決めました。
YouTube運用失敗を回避する成功企業の事例
YouTube運用で失敗を回避し、成功を収めている企業の事例をご紹介します。
武田塾チャンネル|参考書のやり方・大学受験情報
大学受験生にむけた勉強法、参考書を紹介するチャンネルで、登録者数は23.5万人です。武田塾は「日本初、授業をしない塾」というコンセプトを掲げることで、ブランドの拡張、浸透に成功しています。
受験勉強に独学で取り組む受験生は、YouTubeといったメディアで情報収集をすることが多いため、武田塾はそういった層を対象に有用な情報を発信しています。企業色を抑えつつ、ターゲットにとって価値のある情報を提供している好例です。
LUSH JAPAN ラッシュ ジャパン
オーガニックでフレッシュな、ハンドメイドの化粧品の製造過程や使用方法を公開しているチャンネルで、登録者数は1.6万人です。実際に化粧品の製造される工程や使われる場面を動画にすることによって、ラッシュジャパンの「ナチュラル」なイメージがより強固になっています。
また、人権擁護・人道支援、動物権利擁護、環境保護等の活動をミッションの一つとしており、動画でそれらの活動を発信することにより、視聴者の共感を得ることに成功しています。
株式会社 明治
芸能人をはじめとした、影響力のある人たちを起用した商品PRを公開しているチャンネルで、登録者数は8.1万人です。女性に向けたシェイプアップのプロテインを紹介する際は、元オリンピック新体操日本代表の畠山愛理さんを起用するなど、商品と起用する有名人のイメージに統一感を持たせることで、視聴者の関心を高めることに成功しています。
YouTube運用失敗を避けるためのチェックリスト
最後に、YouTube運用で失敗を避けるためのチェックリストをご用意しました。定期的にこのチェックリストを確認し、運用の方向性を見直してください。
戦略・企画段階のチェックポイント
- 運用目的とKPIが明確に設定されているか
- ターゲットユーザーのペルソナが詳細に設定されているか
- 競合チャンネルの分析が十分に行われているか
- 差別化ポイントが明確になっているか
- 長期的な運用計画が策定されているか
制作段階のチェックポイント
- ユーザーにとって価値のあるコンテンツになっているか
- 企業色を抑えた内容になっているか
- エンタメ性や教育性が盛り込まれているか
- 視聴者の興味を惹くサムネイル・タイトルになっているか
- 適切な長さの動画になっているか
運用・分析段階のチェックポイント
- 定期的にYouTubeアナリティクスをチェックしているか
- 数値データに基づいた改善が行われているか
- チーム体制が整っているか
- 継続的な更新ができているか
- 長期的な視点で運用を続けているか
まとめ
YouTube運用失敗の原因と改善策について詳しく解説してきました。
今回の記事のポイントをおさらいしましょう。
・YouTube運用で最も避けるべきは企業視点の自己満足コンテンツの制作
・短期的な結果を求めすぎず、2-3年の長期戦を覚悟して取り組む
・動画投稿後の分析・改善が成功の鍵を握る
・バズを狙うよりも見込み顧客への価値提供を重視する
・適切な運用体制を整えずに始めると必ず失敗する
YouTube運用は決して簡単ではありませんが、適切な戦略と継続的な改善により、必ず成果を出すことができます。