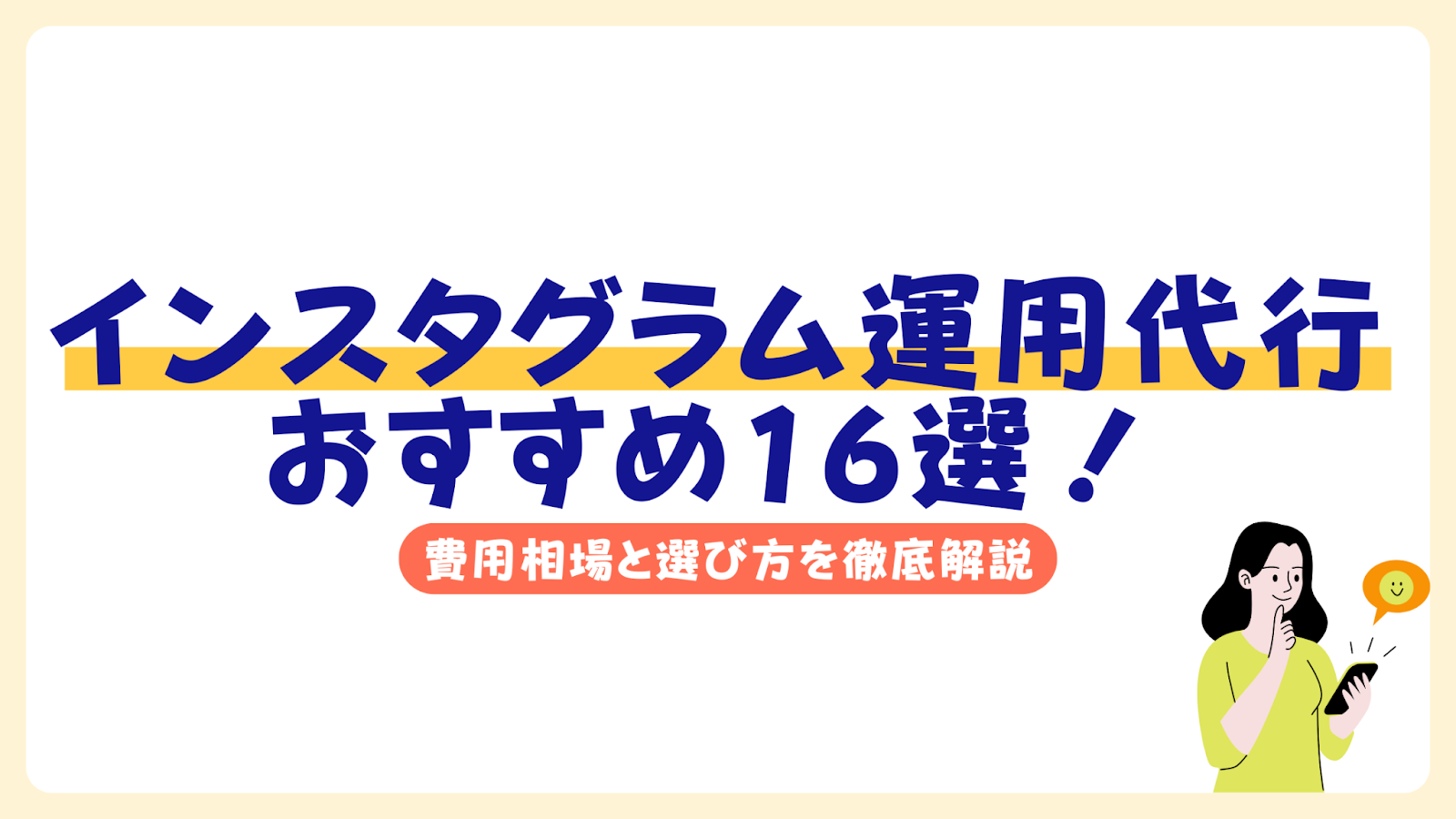【保存版】YouTube運用稟議書の書き方|費用対効果の見せ方とテンプレート完全ガイド

企業のYouTube運用を開始する際、経営陣や上司からの承認を得るために必要不可欠なのがYouTube運用稟議書の作成です。単なる動画制作の提案ではなく、戦略的なマーケティング施策として説得力のある稟議書を作成することで、予算確保と組織的なサポートを得ることができます。
本記事では、YouTube運用稟議書の効果的な書き方から、承認率を高めるポイント、実際に使える無料テンプレートまで、実践的な情報を網羅的に解説します。マーケティング担当者や企画担当者の方にとって、すぐに活用できる具体的な手法をお届けします。

東京大学卒業後、金融機関、スタートアップベンチャーを経て2016年にサイバーエージェントに入社してインターネット広告事業に従事した後、2020年7月に独立しました。
特に広告領域においてはプランニングから運用まで幅広く携わり、ナレッジは日本トップレベルだと自負しています。
◆ 経歴
2014:東京大学行動文化学科 卒業
2014:住友生命保険相互会社 入社
2015:株式会社RoseauPensant 入社
2016:株式会社サイバーエージェント 入社
2020:株式会社CYANd 創業/代表取締役就任
2022:株式会社Minato 入社/広告事業責任者就任
YouTube運用稟議書作成時のよくある課題
企業でYouTube運用の稟議書を作成する際、多くの担当者が以下のような悩みを抱えています。
社内フォーマットがない・使えない問題
会社にYouTube運用専用のフォーマットがなく、一から作成する手間がかかってしまいます。既存のフォーマットがあったとしても、YouTube運用の特性に合わず、毎回大幅なカスタマイズが必要になることも少なくありません。
実際に、マーケティング支援を行う中で「稟議書の作成に時間を取られて、本来の企画検討に集中できない」という相談をよく受けます。
説得力のあるストーリー構成の難しさ
YouTube運用の必要性を論理的に説明し、経営陣を納得させるストーリーを作るのは簡単ではありません。特に、動画マーケティングに馴染みのない経営陣に対して、投資対効果を分かりやすく伝える構成を考えるのに苦労する担当者が多いのが現状です。
費用対効果の算出と根拠提示の困難
投資対効果を定量的に示し、予算承認を得るための根拠作成に苦労する担当者が多いのが現状です。YouTube運用は従来の広告とは異なる効果測定が必要で、どのような指標を使って効果を示すべきか迷ってしまうケースがよく見られます。
YouTube運用稟議書テンプレートの種類と使い分け
効果的な稟議書作成には、状況に応じた適切なアプローチが必要です。今回ご紹介するテンプレートには、「目標達成型」と「危機感醸成型」の2種類があります。
目標達成型テンプレートの特徴
既存の事業目標や中期経営計画と関連付けてYouTube運用の必要性を示すアプローチです。以下のようなストーリーで構成されます:
- 目標は○○ですよね
- 現在△△のような課題があり、○○を達成できません
- YouTube運用を導入することで△△を解消します
- そのためにYouTube運用を開始させてください
起案内容と目標に整合性、合理性があれば稟議は比較的通りやすいのが特徴です。
危機感醸成型テンプレートの活用場面
組織の課題意識が乏しい場合や、起案内容と事業目標の関連性が薄い場合に有効なテンプレートです。市場や競合の状況を提示し、以下のようなストーリーでアプローチします:
- 現在、市場は○○な状況です
- さらに今後は△△といった状況が予想されます
- 当社もいま取り組まないと取り残されます
- そのためにYouTube運用を導入させてください
それぞれのテンプレートの選択基準
基本的には目標達成型で進めることをおすすめしますが、以下のどちらかに当てはまる場合は危機感醸成型を選択するとよいでしょう:
- 事業目標とは関係のない領域での提案
- 稟議関与者、決裁者がリスクマネジメントを重視するタイプ
YouTube運用稟議書に必ず含めるべき8つの要素
効果的な稟議書は、8つの重要なスライドで構成されます。「市場環境」以外は、目標達成型・危機感醸成型ともに共通の内容です。
市場環境の分析(危機感醸成型のみ)
競合他社のYouTube活用状況や市場トレンドを定量的に示し、自社の立ち位置を明確化します。危機感を醸成するために、以下の2点を意識して作成しましょう。
定性ではなく、定量で示す
- NG例:大幅に増加
- OK例:前年比150%増加
解釈ではなく、事実を記載する
- NG例:成長していると推察できる
- OK例:3年連続で売上が増加している
PEST分析や近未来予測、他社の事例を引用し、「自社も取り組まなければ競争に負けてしまうかもしれない」というマインドを醸成できれば成功です。
承認依頼と目的の明確化
YouTube運用開始の承認を求める理由と、達成したい目標を端的に伝える重要なスライドです。長文や専門的な単語を多用すると、心理面も含めて「導入コストがかかる」と受け取られてしまう可能性があります。
以下の点を意識して記載しましょう。
- 膨大な工数やストレスはかからないと印象づける
- 普段使っている言葉を用い、訴求力を高める
- 端的に記載する
YouTube運用が必要な理由の論理的説明
現在の課題と、それがどのようにYouTube運用によって解決されるかを客観的に説明します。目標や取り組みたいことに対する阻害要因を、課題①②として記載します。
普段から課題にあがっていることを記載するのがベストです。経営会議や営業会議で上層部がよく言葉にすることを整理してみましょう。もちろん関係者へのヒアリングも有効です。
実施ロードマップの詳細計画
目標達成までの具体的なスケジュールと、各段階での取り組み内容を示します。これは稟議書の中でも特に重要なスライドの一つです。
局所的、短期的な視点で提案しているのではなく、後の発展性や中期経営計画との関連性を考慮していることを示します。そうすることで、稟議関与者や決裁者の心証が格段に良くなります。
場合によっては、単年ではなく複数年をまたいだ予算を捻出したり、特別費用として新たに予算を確保できたりするケースもあります。精度の高いロードマップを作成しましょう。
費用対効果の定量的算出
投資額に対する期待効果を売上、コスト削減、生産性向上などの観点から数値で示します。費用対効果は定量的に示すことが鉄則です。一般的に売上、費用、生産性、作業時間などの項目を採用します。
手間はかかりますが、これらに加えて、ベター・ベスト・ワーストの感度分析、パターン分けしたシナリオ分析まで行えば完璧と言えるでしょう。
また、副次的効果があれば記載しましょう。とくに従業員満足度やモチベーションの向上といったエモーショナルなものは刺さりやすいです。
類似サービスとの比較検討結果
YouTube以外の動画プラットフォームとの比較により、YouTube選択の合理性を証明します。目標達成に寄与する項目、経営側が重視する項目を整理した一覧表を作成します。
ポイントは、評点の根拠を簡潔に記載し、追加で質問された場合にも評点の根拠をしっかりと答えられるようにしておくこと。とくに「◎と○の判断基準は?」は、頻出の質問です。矛盾を突かれないよう、しっかりと準備しておきましょう。
なお、◎と○について明確な基準はない、というケースがほとんどで、相対評価で最も良いものを「◎」、次点のものを「○」とすることが多いです。
想定リスクと対策の事前提示
運用開始後に発生する可能性のあるリスクと、それぞれの対応策を事前に示します。YouTube運用にはリスクがつきもの。指摘された後に調査しているようでは、提案の説得力がなくなってしまいます。
また、稟議関与者や決裁者も「分析が甘いからほかにも見落としがあるはずだ」と、粗探ししたくなるものです。
事前にリスクを示せば、多角的な調査をしていると受け取ってもらえます。同時に、YouTube運用後のクライシスマネジメントにもつながります。
社内の声とニーズの裏付け
従業員アンケートや関係部署のヒアリング結果により、社内のYouTube運用への期待を示します。このスライドの使用は任意ですが、社内の声は強力なメッセージとなります。
事前にアンケートが取れるようであれば、ぜひ実施しましょう。稟議関与者や決裁者も、「あまり乗り気ではないが、これだけの社員が賛成しているのであれば否決すると士気が下がってしまうかもしれない」と危惧します。
また、アンケートで賛成を集めるために、専門家による勉強会を開催することも有効です。
承認率を高める稟議書作成のポイント
稟議書の承認を得るためには、以下のポイントを意識することが重要です。
定量データによる客観的根拠の提示
感情的な訴求ではなく、市場データや競合分析結果に基づいた論理的な提案を行います。「YouTubeが流行っているから」ではなく、「競合他社の70%がYouTube運用を開始し、平均でリード獲得コストが30%削減されている」といった具体的なデータを示しましょう。
専門用語を避けた分かりやすい説明
経営層にとって理解しやすい言葉を使い、導入コストが高くない印象を与える表現を心がけます。「エンゲージメント率」ではなく「視聴者の反応率」、「CPM」ではなく「1000人あたりの広告費」など、馴染みのある言葉に置き換えることで理解度が大幅に向上します。
段階的投資によるリスク軽減提案
初期は小規模からスタートし、成果に応じて段階的に拡大する現実的な投資プランを提示します。「いきなり年間500万円」ではなく、「まず3か月間100万円でテスト運用し、効果が確認できれば本格展開」という段階的なアプローチを提案することで、経営陣の心理的ハードルを大幅に下げることができます。
YouTube運用稟議書の無料テンプレートと記入方法
実際の稟議書作成を効率化するために、以下のテンプレートを活用することをおすすめします。
目標達成型テンプレートの活用法
既存の事業目標と連動させたYouTube運用提案に最適なテンプレートです。中期経営計画や四半期目標が明確になっている企業では、このテンプレートを使用することで説得力のある提案書を効率的に作成できます。
テンプレートには記入例も含まれているため、自社の状況に合わせてカスタマイズするだけで、すぐに使用可能です。
危機感醸成型テンプレートの使い方
市場環境の変化を強調し、YouTube運用の緊急性を訴える稟議書の作成に適したテンプレートです。特に、デジタル変革が遅れている業界や、競合他社に後れを取っている状況で効果的です。
マーケット分析のスライドから始まることで、「今すぐ行動しなければならない」という危機感を醸成し、YouTube運用への投資を正当化できます。
各スライドの効果的な記入方法
テンプレートの各項目について、以下のポイントを意識して記入しましょう:
承認依頼スライド: 「YouTube運用により○○を△△%向上させる」といった具体的な成果目標を明記
必要理由スライド: 現状の課題を定量的に示し、YouTube運用による解決策を論理的に説明
ロードマップスライド: 3か月、6か月、1年後のマイルストーンを明確に設定
費用対効果スライド: 初期投資、ランニングコスト、期待効果を項目別に詳細化
よくある失敗パターンと回避方法
YouTube運用稟議書作成でよく見られる失敗例と、それを防ぐための具体的な対策を紹介します。
抽象的な目標設定による承認率低下
「ブランド認知向上」などの曖昧な表現ではなく、「ブランド認知度を6か月で15%向上」のような具体的で測定可能な目標設定が不可欠です。経営陣は投資対効果を重視するため、曖昧な目標では承認を得ることが困難になります。
具体的な改善例:
- NG: 「認知度を向上させる」
- OK: 「ターゲット層での認知度を現在の25%から40%に向上」
予算算出根拠の不明確さによる却下リスク
「制作費100万円」ではなく、撮影費・編集費・人件費の詳細内訳を示し、相見積もりの結果も含めた透明性の高い予算提示が必要です。経営陣は予算の妥当性を厳しくチェックするため、根拠が不明確な費用項目があると稟議全体の信頼性が損なわれます。
効果的な予算提示例:
- 企画・撮影費: 30万円(A社見積もり28万円、B社見積もり32万円)
- 編集・制作費: 20万円(月2本×10万円)
- 広告宣伝費: 50万円(YouTube広告:月10万円×5か月)
競合分析不足による説得力の欠如
表面的な競合調査ではなく、チャンネル登録者数・エンゲージメント率・投稿頻度まで分析した詳細な競合レポートの作成が重要です。「競合他社もやっているから」という理由だけでは説得力に欠けるため、具体的な数値データに基づいた分析が必要です。
稟議書作成の効率化テクニック
YouTube運用稟議書の作成負荷を軽減しながら、質の高い提案書を作る実践的なテクニックを解説します。
ベンダー資料の効果的な活用方法
すべてを一から作成する必要はありません。YouTube広告の媒体資料やマーケティング会社の提案書を組み合わせることで、必要最小限の自作資料で完成度の高い稟議書を作成できます。
重要なのは、どのページを自作し、どのページを既存資料で代用するかの判断です。承認に直結する8つの要素は自作し、技術的な説明や事例紹介はベンダー資料を活用するのが効率的です。
社内勉強会を活用した賛同者獲得
稟議提出前に、YouTube運用に関する社内セミナーを開催し、社内の理解と賛同を得る戦略的なアプローチが効果的です。「YouTube運用について社内勉強会をしたい。人選や交渉はすべて自分の方で行う」と会社側へ打診し、外部専門家を招いた勉強会を開催しましょう。
これにより、稟議書の「社内の声」セクションで具体的なアンケート結果を提示でき、説得力が大幅に向上します。
まとめ
YouTube運用稟議書の作成について、承認を得るためのポイントから実践的なテンプレートまで詳しく解説してきました。
今回の記事のポイントをおさらいしましょう。
・YouTube運用稟議書は目標達成型と危機感醸成型の2種類のアプローチがある
・8つの必須要素を含めることで説得力のある提案書を作成できる
・定量的なデータと具体的な根拠により承認率を大幅に向上させられる
・想定リスクの事前提示により、多角的な検討をしている印象を与えられる
・ベンダー資料の活用で作成負荷を軽減しながら完成度を高められる
・提出後のフォローアップと継続的な効果報告が長期的な投資確保につながる
適切に作成されたYouTube運用稟議書は、単なる承認取得のツールを超えて、成功するYouTube運用の設計図としても機能することでしょう。